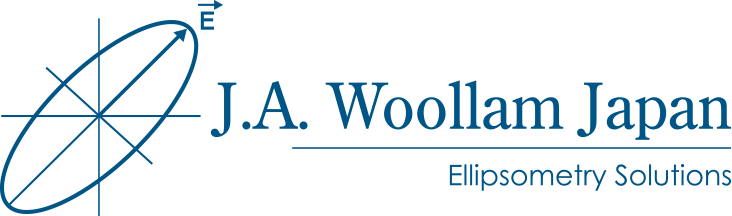光と物質
光と物質がどのように相互作用するかを記述する値である光学定数には、2つの表記方法があり、一般に複素数として表されます。複素屈折率は次式のように屈折率nと消衰係数kで構成されています。

あるいは、光学定数は複素誘電関数としても表すこともできます。

両者には次の関係があります。

屈折率nは、真空中の光の速度cと比較した物質中での光の位相速度を記述します。

屈折率が大きい物質に進入すると光の速度は遅くなります。これは光の振幅は一定ですが、波長は短くなるためです。
消衰係数kは物質中での光のエネルギーの損失を表しています。これは次の式で表される吸収係数αに関係しています。

吸収のある物質中では、光はベールの法則に従い強度を失います。

そのため、消衰係数は光が物質中でどれだけ急速に減衰するかに関係しています。これらの概念を図2に示します。この図では光学定数が異なる2つの物質に光が進入する例を示しています。

図2:吸収膜Film1と透明膜Film2に光が進入している例。位相速度と波長がそれぞれの屈折率に依存して変化している(Film1: n=4, Film2: n=2)。
図3は紫外(UV)から赤外(IR) の波長領域におけるTiO2の光学定数を示しています。波長によって光学定数が異なっており、紫外と赤外では異なる要因により生じている吸収(k>0)が見られます。赤外領域での吸収は一般的に分子振動や格子振動、フリーキャリアによるものです。紫外での吸収は電子遷移、つまり光の入射による電子のエネルギー準位の励起が要因であることが一般的です。図3中の光学定数の実部と虚部は形状が似ていますが、これは実部と虚部が独立した値でないことを示しており、クラマース・クローニヒの関係で数学的に結び付いています。

Complex dielectric function for TiO2 film covering wavelengths from the infrared (small eV) to the ultraviolet (high eV).